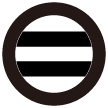
遠山美濃守邸(とおやまみのかみ)(苗木藩)
苗木藩(岐阜県中津川市苗木)
関ヶ原の戦いにおいて出陣中で留守城であった苗木城を、河尻秀長がわずかな手勢で奪い、その功として家康よりそのまま苗木城を賜る。大名は鉢植えという徳川幕府の大名政策のなかで、遠山家は武力で城を取り、そのまま中世以来の城を明治まで領有として全うした希有な存在といえる。石高1万石で城主大名というのも、この苗木藩の遠山家だけ。
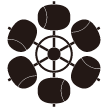
土井大炊頭邸(どいおおいのかみ)(古河藩)
古河藩(茨城県古河市)
土井家は関ヶ原の戦いで東軍につき、土井大炊頭利勝(どいおおいのかみとしかつ・1573年~1644年)は、三代将軍徳川家光の輔導役を務めた。利勝は三河土居出身の武将・土居利昌の長男といわれているが、出生は謎に満ちている。古河藩は延べ12家が入れ替わり藩主を務めているが、譜代大名として肥前唐津から土井家が復帰してから以後は定着し、幕末まで土井家が7代継いだ。古河藩の第6代藩主土井利則(どい としのり・1831年~1891年)は、西洋砲術の演習、武芸の奨励、片町教武所の創設などに尽力した。
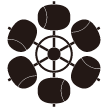
土井大炊頭邸(どいおおいのかみ)(古河藩)
古河藩(茨城県古河市)
土井家は関ヶ原の戦いで東軍につき、土井大炊頭利勝(どいおおいのかみとしかつ・1573年~1644年)は、三代将軍徳川家光の輔導役を務めた。利勝は三河土居出身の武将・土居利昌の長男といわれているが、出生は謎に満ちている。古河藩は延べ12家が入れ替わり藩主を務めているが、譜代大名として肥前唐津から土井家が復帰してから以後は定着し、幕末まで土井家が7代継いだ。古河藩の第6代藩主土井利則(どい としのり・1831年~1891年)は、西洋砲術の演習、武芸の奨励、片町教武所の創設などに尽力した。
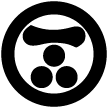
永井飛騨守邸(ながいひだのかみ)(高槻藩)
高槻藩(大阪府高槻市)
17世紀半ばに山城長岡藩より永井直清(ながい なおきよ・1591年~1671年)が3万6千石で高槻藩に入り、高槻藩は以後、永井家13代の支配で明治を迎えた。なお、有楽稲荷神社は、高槻藩第11代藩主永井直輝が藩邸内に建立した屋敷神で、天下泰平と子孫繁栄を祈念して1859年に創立したもの。1973年の有楽町電気ビルの新築に伴い、一時、赤坂山王日枝神社に遷座されたが、1979年2月に再びこの地に復座した。
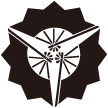
松平右京亮邸(まつだいらうきょうのすけ)(高崎藩)
高崎藩(群馬県高崎市)
松平(大河内)輝貞(まつだいらおおこうち てるさだ・1665年~1747年)が吉宗に再度用いられ老中となって高崎藩に返り咲いてからは、高崎藩は松平(大河内)家が支配し幕末に至る。第11代藩主で陸軍奉行の松平右京亮輝声(輝聲)(まつだいらうきょうのすけてるな<てつあき>・1848年~1882年)は三代家光の老中を務めた松平信綱の五男の家の血統で、漢学的教養による中国文化愛好者としても知られる。1868年に松平姓を改め、本姓の大河内に復し、翌年高崎藩知事に任じられる。
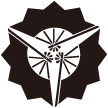
松平右京亮邸(まつだいらうきょうのすけ)(高崎藩)
高崎藩(群馬県高崎市)
松平(大河内)輝貞(まつだいらおおこうち てるさだ・1665年~1747年)が吉宗に再度用いられ老中となって高崎藩に返り咲いてからは、高崎藩は松平(大河内)家が支配し幕末に至る。第11代藩主で陸軍奉行の松平右京亮輝声(輝聲)(まつだいらうきょうのすけてるな<てつあき>・1848年~1882年)は三代家光の老中を務めた松平信綱の五男の家の血統で、漢学的教養による中国文化愛好者としても知られる。1868年に松平姓を改め、本姓の大河内に復し、翌年高崎藩知事に任じられる。

松平土佐守邸(まつだいらとさのかみ)(土佐藩)
土佐藩(高知県全域)
山内家は山内一豊(やまうち かつとよ・1545年~1605年)が関ヶ原の戦いで徳川方に参加し、土佐一国を与えられたことに端を発す外様大名。以降、一貫して廃藩置県まで山内家が土佐藩を治める。第15代藩主山内容堂(豊信)(やまうち ようどう<とよしげ>・1827年~1872年)は藩政改革を断行し幕末の四賢侯の一人として評価されるが、公武合体派で藩内の勤皇志士を弾圧する一方、朝廷にも奉仕した。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平相模守邸(まつだいらさがみのかみ)(鳥取藩)
鳥取藩(鳥取県全域)
1632年に突然の国替えによって備前から移ってきた池田光仲(いけだ みつなか・1630年~1693年)が鳥取藩を治めるようになり、以後、池田家の分家筋が幕末まで鳥取藩を治めることとなる。松平(鳥取池田)家は、徳川家と遠縁にあたり外様大名でありながら松平姓と葵紋が下賜され親藩に準ずる家格が与えられた。第12代藩主池田慶徳(いけだ よしのり・1837年~1877年)は徳川慶喜(とくがわ よしのぶ・1837年~1913年)の異母兄にあたり、藩の財政難などのこともあり藩主の立場にありながら廃藩置県を自ら明治政府に提案したという。

松平能登守邸(まつだいらのとのかみ)(岩村藩)
岩村藩(岐阜県恵那市の一部)
松平(大給)能登守家は、松平乗紀(まつだいら のりただ・1674年~1717年)が1702年に美濃岩村藩初代藩主となる。1855年に家督を相続した第7代藩主松平乗命(まつだいら のりとし・1848年~1905年)は同年能登守に叙位・任官。1867年に陸軍奉行に任じられるが、1868年には新政府に恭順している。
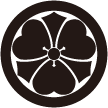
酒井飛騨守邸(さかいひだのかみ)(敦賀藩)
敦賀藩(福井県敦賀市)
小浜藩の第2代藩主酒井忠直(さかい ただなお・1630年~1682年)の遺志に基づいて、次男・忠稠(ただしげ・1653年~1706年)が1万石を分与され、小浜藩の支藩である敦賀藩を1682年に立藩し初代藩主となる。以降、明治まで酒井家が支配する。第13代藩主酒井忠氏(さかい ただうじ・1835年~1876年)は幕末期の動乱のなかでは佐幕派として行動し、天狗党の乱鎮圧などで功績を挙げている。戊辰戦争でも幕府軍の一員として官軍と戦った。
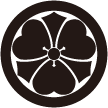
酒井飛騨守邸(さかいひだのかみ)(敦賀藩)
敦賀藩(福井県敦賀市)
小浜藩の第2代藩主酒井忠直(さかい ただなお・1630年~1682年)の遺志に基づいて、次男・忠稠(ただしげ・1653年~1706年)が1万石を分与され、小浜藩の支藩である敦賀藩を1682年に立藩し初代藩主となる。以降、明治まで酒井家が支配する。第13代藩主酒井忠氏(さかい ただうじ・1835年~1876年)は幕末期の動乱のなかでは佐幕派として行動し、天狗党の乱鎮圧などで功績を挙げている。戊辰戦争でも幕府軍の一員として官軍と戦った。
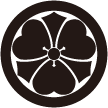
酒井飛騨守邸(さかいひだのかみ)(敦賀藩)
敦賀藩(福井県敦賀市)
小浜藩の第2代藩主酒井忠直(さかい ただなお・1630年~1682年)の遺志に基づいて、次男・忠稠(ただしげ・1653年~1706年)が1万石を分与され、小浜藩の支藩である敦賀藩を1682年に立藩し初代藩主となる。以降、明治まで酒井家が支配する。第13代藩主酒井忠氏(さかい ただうじ・1835年~1876年)は幕末期の動乱のなかでは佐幕派として行動し、天狗党の乱鎮圧などで功績を挙げている。戊辰戦争でも幕府軍の一員として官軍と戦った。
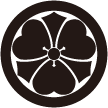
酒井飛騨守邸(さかいひだのかみ)(敦賀藩)
敦賀藩(福井県敦賀市)
小浜藩の第2代藩主酒井忠直(さかい ただなお・1630年~1682年)の遺志に基づいて、次男・忠稠(ただしげ・1653年~1706年)が1万石を分与され、小浜藩の支藩である敦賀藩を1682年に立藩し初代藩主となる。以降、明治まで酒井家が支配する。第13代藩主酒井忠氏(さかい ただうじ・1835年~1876年)は幕末期の動乱のなかでは佐幕派として行動し、天狗党の乱鎮圧などで功績を挙げている。戊辰戦争でも幕府軍の一員として官軍と戦った。
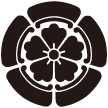
織田兵部少輔邸(おだひょうぶしょうゆう)(天童藩)
天童藩(山形県天童市)
織田信長の次男信雄系信良流織田氏当主の織田信美(おだ のぶかず・1793年~1836年)が天童藩初代藩主となる。第2代目藩主織田信学(おだ のぶみち・1819年~1891年)は幕末の動乱期に入ると、藩財政の悪化から紅花の専売制や年貢の前納化を実施。しかし、うまくいかず「裸裸足で紅花さしても織田に取られて因果因果」と歌われた民謡までできた。
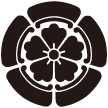
織田兵部少輔邸(おだひょうぶしょうゆう)(天童藩)
天童藩(山形県天童市)
織田信長の次男信雄系信良流織田氏当主の織田信美(おだ のぶかず・1793年~1836年)が天童藩初代藩主となる。第2代目藩主織田信学(おだ のぶみち・1819年~1891年)は幕末の動乱期に入ると、藩財政の悪化から紅花の専売制や年貢の前納化を実施。しかし、うまくいかず「裸裸足で紅花さしても織田に取られて因果因果」と歌われた民謡までできた。
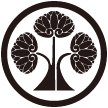
本多美濃守邸(ほんだみののかみ)(岡崎藩)
岡崎藩(愛知県岡崎市周辺)
徳川四天王の一人本田忠勝系本多家宗家11代の本多忠粛(ほんだ ただとし・1759年~1777年)が1769年に5万石で岡崎藩主となり、以降忠勝系本多家が6代継いで明治維新を迎える。岡崎藩主第5代本多忠民(ほんだ ただもと・1817年~1883年)は1835年に家督を継ぎ、1846年に寺社奉行となる。1857年には京都所司代となり朝廷対策、特に条約締結問題で朝幕間を奔走。1860年から老中を務める。戊辰戦争では岡崎藩を新政府恭順に統一した。
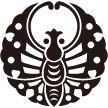
松平内蔵頭邸(まつだいらくらのかみ)(岡山藩)
岡山藩(岡山県岡山市)
1632年に池田光政(いけだ みつまさ・1609年~1682年)が岡山藩に入封して以降、明治まで松平池田岡山家が岡山藩を治める。光政は、徳川光圀(とくがわ みつくに・1628年~1701年)、保科正之(ほしな まさゆき・1611年~1672年)と並び江戸三名君と称された。また、全国初の藩校である花畠教場を開校したことでも知られる。また、教育の充実と質素倹約を旨とし「備前風」といわれる政治姿勢を確立した。第9代藩主池田茂政(いけだ もちまさ・1839年~1899年)の父は徳川斉昭(とくがわ なりあき・1800年~1860年)で、第15代将軍慶喜は兄になる。
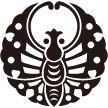
松平内蔵頭邸(まつだいらくらのかみ)(岡山藩)
岡山藩(岡山県岡山市)
1632年に池田光政(いけだ みつまさ・1609年~1682年)が岡山藩に入封して以降、明治まで松平池田岡山家が岡山藩を治める。光政は、徳川光圀(とくがわ みつくに・1628年~1701年)、保科正之(ほしな まさゆき・1611年~1672年)と並び江戸三名君と称された。また、全国初の藩校である花畠教場を開校したことでも知られる。また、教育の充実と質素倹約を旨とし「備前風」といわれる政治姿勢を確立した。第9代藩主池田茂政(いけだ もちまさ・1839年~1899年)の父は徳川斉昭(とくがわ なりあき・1800年~1860年)で、第15代将軍慶喜は兄になる。
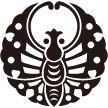
松平内蔵頭邸(まつだいらくらのかみ)(岡山藩)
岡山藩(岡山県岡山市)
1632年に池田光政(いけだ みつまさ・1609年~1682年)が岡山藩に入封して以降、明治まで松平池田岡山家が岡山藩を治める。光政は、徳川光圀(とくがわ みつくに・1628年~1701年)、保科正之(ほしな まさゆき・1611年~1672年)と並び江戸三名君と称された。また、全国初の藩校である花畠教場を開校したことでも知られる。また、教育の充実と質素倹約を旨とし「備前風」といわれる政治姿勢を確立した。第9代藩主池田茂政(いけだ もちまさ・1839年~1899年)の父は徳川斉昭(とくがわ なりあき・1800年~1860年)で、第15代将軍慶喜は兄になる。
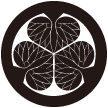
松平三河守邸(まつだいらみかわのかみ)(津山藩)
津山藩(岡山県津山市)
松平宣富(まつだいら のぶとみ・1680年~1721年)が1698年に10万石で津山藩に入封し、廃藩置県まで松平(越前)家が治める。第9代(最後の)藩主松平慶倫(まつだいら よしとも・1827年~1871年)は藩内の尊王攘夷派の排斥を行い、1869年に版籍奉還によりに津山藩知事に任じられる。なお、松平(越前)家は徳川家康の二男秀康を家祖とする一門全体を指す場合と、その領地の場所から福井松平家のみをさす場合がある。
松平丹波守邸(まつだいらたんばのかみ)(松本藩)
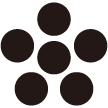
松本藩(長野県松本市)
松平(戸田)家の初代松平康長(まつだいら やすなが・1562年~1633)は家康・秀忠・家光の3代に厚い信任を受けたこともあり、代々源姓松平氏と三つ葉葵を下賜されてきた。1633年に松平直政(まつだいら なおまさ・1601年~1666年)が大野藩より7万石で松本藩に入り、以降は松平(戸田)家が松本藩を治める。1868年の戊辰戦争では藩論が佐幕・勤皇に二分したが、第9代(最後の)藩主松平光則(まつだいら みつひさ・1828年~1892年)は新政府軍の松本到着直前に勤皇に決した。

阿部伊勢守邸(あべいせのかみ)(福山藩)
福山藩(広島県南東部)
1843年、福山藩第7代藩主阿部伊勢守正弘(あべいせのかみまさひろ・1819年~1857年)は弱冠25歳にして水野忠邦の後任として老中に任命され、天保の改革の後始末をすることを期待されるとともに、開国に向けての動きのなかで手腕を発揮する。また第8代(最後の)藩主阿部正恒(あべ まさつね・1839年~1899年)は、江戸城本丸普請を担当。戊辰戦争では新政府と敵対したが敗退。1869年に版籍奉還で佐貫藩知事に任命される。

阿部伊勢守邸(あべいせのかみ)(福山藩)
福山藩(広島県南東部)
1843年、福山藩第7代藩主阿部伊勢守正弘(あべいせのかみまさひろ・1819年~1857年)は弱冠25歳にして水野忠邦の後任として老中に任命され、天保の改革の後始末をすることを期待されるとともに、開国に向けての動きのなかで手腕を発揮する。また第8代(最後の)藩主阿部正恒(あべ まさつね・1839年~1899年)は、江戸城本丸普請を担当。戊辰戦争では新政府と敵対したが敗退。1869年に版籍奉還で佐貫藩知事に任命される。

阿部伊勢守邸(あべいせのかみ)(福山藩)
福山藩(広島県南東部)
1843年、福山藩第7代藩主阿部伊勢守正弘(あべいせのかみまさひろ・1819年~1857年)は弱冠25歳にして水野忠邦の後任として老中に任命され、天保の改革の後始末をすることを期待されるとともに、開国に向けての動きのなかで手腕を発揮する。また第8代(最後の)藩主阿部正恒(あべ まさつね・1839年~1899年)は、江戸城本丸普請を担当。戊辰戦争では新政府と敵対したが敗退。1869年に版籍奉還で佐貫藩知事に任命される。
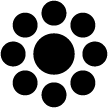
細川越中守邸(ほそかわえっちゅうのかみ)(熊本藩)
熊本藩(熊本県の大部分と大分県の一部)
肥後細川家2代の細川忠利(ほそかわ ただとし・1586年~1641年)が54万石で熊本藩に入封し、以降肥後細川家が領する。第3代藩主細川綱利(ほそかわ つなとし・1643年~1714年)は元禄赤穂事件(忠臣蔵)で、大石良雄らのお預かりを担当したことで知られる。第12代(最後の)藩主細川護久(ほそかわ もりひさ・1839年~1893年)は幕末に弟の長岡護美と共に上京して公武合体に尽力した。なお、丸の内北口ビルのエントランスホールの床にある黒御影石に細川家屋敷跡の線刻が施されている。
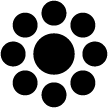
細川越中守邸(ほそかわえっちゅうのかみ)(熊本藩)
熊本藩(熊本県の大部分と大分県の一部)
肥後細川家2代の細川忠利(ほそかわ ただとし・1586年~1641年)が54万石で熊本藩に入封し、以降肥後細川家が領する。第3代藩主細川綱利(ほそかわ つなとし・1643年~1714年)は元禄赤穂事件(忠臣蔵)で、大石良雄らのお預かりを担当したことで知られる。第12代(最後の)藩主細川護久(ほそかわ もりひさ・1839年~1893年)は幕末に弟の長岡護美と共に上京して公武合体に尽力した。なお、丸の内北口ビルのエントランスホールの床にある黒御影石に細川家屋敷跡の線刻が施されている。
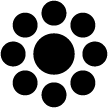
細川越中守邸(ほそかわえっちゅうのかみ)(熊本藩)
熊本藩(熊本県の大部分と大分県の一部)
肥後細川家2代の細川忠利(ほそかわ ただとし・1586年~1641年)が54万石で熊本藩に入封し、以降肥後細川家が領する。第3代藩主細川綱利(ほそかわ つなとし・1643年~1714年)は元禄赤穂事件(忠臣蔵)で、大石良雄らのお預かりを担当したことで知られる。第12代(最後の)藩主細川護久(ほそかわ もりひさ・1839年~1893年)は幕末に弟の長岡護美と共に上京して公武合体に尽力した。なお、丸の内北口ビルのエントランスホールの床にある黒御影石に細川家屋敷跡の線刻が施されている。
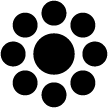
細川越中守邸(ほそかわえっちゅうのかみ)(熊本藩)
熊本藩(熊本県の大部分と大分県の一部)
肥後細川家2代の細川忠利(ほそかわ ただとし・1586年~1641年)が54万石で熊本藩に入封し、以降肥後細川家が領する。第3代藩主細川綱利(ほそかわ つなとし・1643年~1714年)は元禄赤穂事件(忠臣蔵)で、大石良雄らのお預かりを担当したことで知られる。第12代(最後の)藩主細川護久(ほそかわ もりひさ・1839年~1893年)は幕末に弟の長岡護美と共に上京して公武合体に尽力した。なお、丸の内北口ビルのエントランスホールの床にある黒御影石に細川家屋敷跡の線刻が施されている。
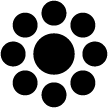
細川越中守邸(ほそかわえっちゅうのかみ)(熊本藩)
熊本藩(熊本県の大部分と大分県の一部)
肥後細川家2代の細川忠利(ほそかわ ただとし・1586年~1641年)が54万石で熊本藩に入封し、以降肥後細川家が領する。第3代藩主細川綱利(ほそかわ つなとし・1643年~1714年)は元禄赤穂事件(忠臣蔵)で、大石良雄らのお預かりを担当したことで知られる。第12代(最後の)藩主細川護久(ほそかわ もりひさ・1839年~1893年)は幕末に弟の長岡護美と共に上京して公武合体に尽力した。なお、丸の内北口ビルのエントランスホールの床にある黒御影石に細川家屋敷跡の線刻が施されている。

小笠原左京大夫邸(おがさわらさきょうのだいぶ)(小倉藩)
小倉藩(福岡県北九州市とその周辺)
1632年に豊前小倉城に15万石で転封し初代藩主となった小笠原忠真(おがさわら ただざね・1596年~1667年)は、島原の乱の際には長崎守備の任を果たした。また、大名茶人でもあり、同地の茶湯隆盛の基盤を築いた。第10代(最後の)藩主小笠原忠忱(おがさわら ただのぶ・1862年~1897年)は6歳のときに家督を継ぐこととなる。幼少だったため、家老の小宮民部らの補佐を受けた。第二次長州征伐では長州との戦争を避けるため小倉城に火を放って田川郡香春に移る。

小笠原左京大夫邸(おがさわらさきょうのだいぶ)(小倉藩)
小倉藩(福岡県北九州市とその周辺)
1632年に豊前小倉城に15万石で転封し初代藩主となった小笠原忠真(おがさわら ただざね・1596年~1667年)は、島原の乱の際には長崎守備の任を果たした。また、大名茶人でもあり、同地の茶湯隆盛の基盤を築いた。第10代(最後の)藩主小笠原忠忱(おがさわら ただのぶ・1862年~1897年)は6歳のときに家督を継ぐこととなる。幼少だったため、家老の小宮民部らの補佐を受けた。第二次長州征伐では長州との戦争を避けるため小倉城に火を放って田川郡香春に移る。

小笠原左京大夫邸(おがさわらさきょうのだいぶ)(小倉藩)
小倉藩(福岡県北九州市とその周辺)
1632年に豊前小倉城に15万石で転封し初代藩主となった小笠原忠真(おがさわら ただざね・1596年~1667年)は、島原の乱の際には長崎守備の任を果たした。また、大名茶人でもあり、同地の茶湯隆盛の基盤を築いた。第10代(最後の)藩主小笠原忠忱(おがさわら ただのぶ・1862年~1897年)は6歳のときに家督を継ぐこととなる。幼少だったため、家老の小宮民部らの補佐を受けた。第二次長州征伐では長州との戦争を避けるため小倉城に火を放って田川郡香春に移る。
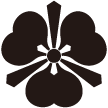
酒井雅楽頭邸(さかいうたのかみ)(姫路藩)
姫路藩(兵庫県姫路市と県西南部)
世界遺産になった国宝・姫路城で有名な姫路藩は1749年以降10代にわたり雅楽頭系酒井家が治める。雅楽頭系酒井家宗家2代酒井忠世(さかい ただよ・1572年~1636年)は、家康、秀忠、家光の3代にわたり仕える。その孫にあたる酒井忠清は4大将軍家綱の時代に大老となる。また、第8代藩主酒井忠績(さかい ただしげ・1827年~1895年)は最後の大老として、第2次長州征伐の事後処理、幕府軍の西洋式軍制の導入など幕政改革に尽力した。
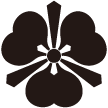
酒井雅楽頭邸(さかいうたのかみ)(姫路藩)
姫路藩(兵庫県姫路市と県西南部)
世界遺産になった国宝・姫路城で有名な姫路藩は1749年以降10代にわたり雅楽頭系酒井家が治める。雅楽頭系酒井家宗家2代酒井忠世(さかい ただよ・1572年~1636年)は、家康、秀忠、家光の3代にわたり仕える。その孫にあたる酒井忠清は4大将軍家綱の時代に大老となる。また、第8代藩主酒井忠績(さかい ただしげ・1827年~1895年)は最後の大老として、第2次長州征伐の事後処理、幕府軍の西洋式軍制の導入など幕政改革に尽力した。
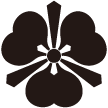
酒井雅楽頭邸(さかいうたのかみ)(姫路藩)
姫路藩(兵庫県姫路市と県西南部)
世界遺産になった国宝・姫路城で有名な姫路藩は1749年以降10代にわたり雅楽頭系酒井家が治める。雅楽頭系酒井家宗家2代酒井忠世(さかい ただよ・1572年~1636年)は、家康、秀忠、家光の3代にわたり仕える。その孫にあたる酒井忠清は4大将軍家綱の時代に大老となる。また、第8代藩主酒井忠績(さかい ただしげ・1827年~1895年)は最後の大老として、第2次長州征伐の事後処理、幕府軍の西洋式軍制の導入など幕政改革に尽力した。
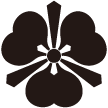
酒井雅楽頭邸(さかいうたのかみ)(姫路藩)
姫路藩(兵庫県姫路市と県西南部)
世界遺産になった国宝・姫路城で有名な姫路藩は1749年以降10代にわたり雅楽頭系酒井家が治める。雅楽頭系酒井家宗家2代酒井忠世(さかい ただよ・1572年~1636年)は、家康、秀忠、家光の3代にわたり仕える。その孫にあたる酒井忠清は4大将軍家綱の時代に大老となる。また、第8代藩主酒井忠績(さかい ただしげ・1827年~1895年)は最後の大老として、第2次長州征伐の事後処理、幕府軍の西洋式軍制の導入など幕政改革に尽力した。
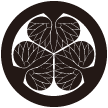
松平越前守邸(まつだいらえちぜんのかみ)(福井藩)
福井藩(福井県東部)
藩祖は徳川家康の二男で2代将軍秀忠(ひでただ・1579年~1632年)の兄結城秀康(ゆうき ひでやす・1574年~1607年)という名門。秀康は結城姓を松平に復し、松平(越前)家を興す。第16代藩主松平春嶽(慶永)(まつだいら しゅんがく<よしなが>・1828年~1890年)は、弱冠11歳で福井藩主となる。財政基盤を盤石にすることに努め、翻訳機関洋楽所の設置や軍制改革などの藩政改革を行う。また、13代将軍家定(いえさだ・1824年~1858年)の継嗣問題では、一橋徳川家当主の慶喜を後押しするが、井伊直弼により隠居・謹慎を命じられ江戸霊岸島に幽閉される。明治維新後は明治新政府の議定、大蔵卿など要職を担った。
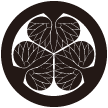
松平越前守邸(まつだいらえちぜんのかみ)(福井藩)
福井藩(福井県東部)
藩祖は徳川家康の二男で2代将軍秀忠(ひでただ・1579年~1632年)の兄結城秀康(ゆうき ひでやす・1574年~1607年)という名門。秀康は結城姓を松平に復し、松平(越前)家を興す。第16代藩主松平春嶽(慶永)(まつだいら しゅんがく<よしなが>・1828年~1890年)は、弱冠11歳で福井藩主となる。財政基盤を盤石にすることに努め、翻訳機関洋楽所の設置や軍制改革などの藩政改革を行う。また、13代将軍家定(いえさだ・1824年~1858年)の継嗣問題では、一橋徳川家当主の慶喜を後押しするが、井伊直弼により隠居・謹慎を命じられ江戸霊岸島に幽閉される。明治維新後は明治新政府の議定、大蔵卿など要職を担った。
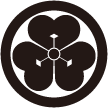
酒井左衛門尉邸(さかいさえもんのじょう)(庄内藩)
庄内藩(山形県鶴岡市)
主家は徳川四天王の一人である酒井忠次(さかい ただつぐ・1527年~1596年)。転封の多い譜代大名にあって、庄内藩酒井家は「三方領地替え」など何度となく転封の危機に晒されながらも、領民の直訴などにより転封が一度もなかった数少ない大名のひとつ。第11代藩主酒井忠篤(さかい ただずみ・1853年~1915年)は、幕末期の動乱のなかでは、譜代大名のなかでも有力な名門出身のため1863年に新徴組を預けられ江戸市中取締役に任じられる。戊辰戦争では幕府軍が敗れた後も奥羽越列藩同盟の一員として新政府軍と戦う。
一橋殿
一橋家は徳川家御三卿(ごさんきょう)のひとつで、八代将軍吉宗(よしむね・1684年~1751年)の四男宗尹(むねただ・1721年~1765年)を祖とする。家格は徳川御三家(尾張徳川家・紀州徳川家・水戸徳川家)に次ぐ。御三卿は、中期に分立した徳川氏の一族で、徳川将軍家に後嗣がない際に将軍の後継者を提供する役割を担う。各家に10万石が給せられていたものの藩は立てず、諸国に分散していた領地の実効支配を幕府から委ねられた。一橋家は御三卿の中で将軍を唯一出し、第11代将軍家斉と第15代将軍慶喜が一橋家出身。
一橋殿
一橋家は徳川家御三卿(ごさんきょう)のひとつで、八代将軍吉宗(よしむね・1684年~1751年)の四男宗尹(むねただ・1721年~1765年)を祖とする。家格は徳川御三家(尾張徳川家・紀州徳川家・水戸徳川家)に次ぐ。御三卿は、中期に分立した徳川氏の一族で、徳川将軍家に後嗣がない際に将軍の後継者を提供する役割を担う。各家に10万石が給せられていたものの藩は立てず、諸国に分散していた領地の実効支配を幕府から委ねられた。一橋家は御三卿の中で将軍を唯一出し、第11代将軍家斉と第15代将軍慶喜が一橋家出身。
一橋殿
一橋家は徳川家御三卿(ごさんきょう)のひとつで、八代将軍吉宗(よしむね・1684年~1751年)の四男宗尹(むねただ・1721年~1765年)を祖とする。家格は徳川御三家(尾張徳川家・紀州徳川家・水戸徳川家)に次ぐ。御三卿は、中期に分立した徳川氏の一族で、徳川将軍家に後嗣がない際に将軍の後継者を提供する役割を担う。各家に10万石が給せられていたものの藩は立てず、諸国に分散していた領地の実効支配を幕府から委ねられた。一橋家は御三卿の中で将軍を唯一出し、第11代将軍家斉と第15代将軍慶喜が一橋家出身。